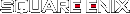この“WE ARE VANA’DIEL”では、これまでおもに『ファイナルファンタジーXI』(以下、『FFXI』)のプロジェクトに携わった開発者や関係者にインタビューを行ってきたが、今回はひとりの冒険者として『FFXI』をプレイしてきた、他業種のクリエイターに注目。配信番組“ファイナルファンタジーXI A.M.A.N.とLIVE!(アマンとライブ!)”への出演をきっかけに、あわせてインタビュー取材を実施させていただいた。その第1弾として、作家である水野良さんへのインタビューをお届けする。
小説やテーブルトークRPG(以下、TRPG。※)のゲームデザインで数々のファンタジー世界を作り上げてきた水野さんの視点から見た『FFXI』とは、どのような作品だったのか。この前編では水野さんとファンタジーとの出会いや、最初にヴァナ・ディールに降り立ったときの思い出を語っていただいた。

作家・ゲームデザイナー。多数のファンタジー小説のほか、『ソード・ワールドRPG』などのTRPGのワールドデザインやリプレイ企画も手掛ける。おもな著作は『ロードス島戦記』(角川スニーカー文庫)、『魔法戦士リウイ』(富士見ファンタジア文庫)、『漂流伝説クリスタニア』(電撃文庫)、『グランクレスト戦記』(富士見ファンタジア文庫)など。
TRPGのあまりのおもしろさに驚いた
まず、『FFXI』に関するお話をうかがう前に、水野先生がファンタジーに興味を持つようになったきっかけ、そしてTRPGやコンピュータRPGに興味を持つようになったきっかけから教えてください。
- 水野
原点にあるのは、小学生のころに図書館などで読んだ、ギリシア神話をはじめとする神話だと思います。もちろん当時読んだものは子ども向けのものだったと思いますが、神々が織り成す物語世界が好きでした。また星も好きだったので、星座に関わる神話はとくに「美しいな」と感じていました。ですからファンタジーへの関心は、そのころから始まっていたと言えるでしょう。
たしかに神話は、多くの人が最初に触れるファンタジーかもしれないですね。
- 水野
その後は中学生時代にSFに惹かれ、高校生時代にはSFのファンダム(ファンコミュニティ)に入る……という流れです。あの当時、SFとファンタジーは細分化されておらず、“SF&ファンタジー”といった感じで地続きのジャンルでした。ハヤカワ文庫さんの“青背”(※1)にもファンタジー作品がありましたから。ほかには“ハヤカワ文庫FT”(※2)も読んでいましたし、そのころは個人的にもSFとファンタジーを区別せずに読んでいたように思います。本格的なファンタジーとの出会いはその時期ですね。
※1……早川書房が発行している文庫レーベル“ハヤカワ文庫SF”において、背表紙が青色のものを指す。当初は背表紙が白の“白背”は口絵や挿絵のある娯楽系SF、背表紙が青の“青背”は口絵や挿絵のない本格SFとされていた。※2……ハヤカワ文庫の中でも海外ファンタジー作品を刊行していたレーベル。 当時は小説以外にファンタジー系のボードゲームなどもあったと思うのですが、そのあたりはすでにプレイされていたのでしょうか?
- 水野
高校生のころに『マジックレルム』(※)など、いくつかは遊んでいます。最初はウォー・シミュレーションゲームを遊んでいて、それがボードゲームとの出会いだったのですが、専門ショップにも行くようになった結果、ファンタジー系のボードゲームも見つけて遊ぶようになりました。当時は仲のよかったいとこといっしょにグループで遊んでいましたね。のちにそのグループはゲームやアニメの同好会のような形に発展していきました。
※1979年に発売されたファンタジー系のボードゲーム。日本語版タイトルは『剣と魔法の国』。ファンタジー世界をゲームマスターなしでシミュレーションゲームとして楽しむことができる。 そういったボードゲームを経て、TRPGに最初に触れたのはいつごろだったのでしょうか?
- 水野
大学1年生のときに安田均さん(※1)にお会いして、TRPGを勧められたんです。いちばん最初に遊んだTRPGは『トラベラー』(※2)でした。その後は『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』の赤箱(※3)も買ったのですが、ルールブックを読むのにすごく時間がかかったことを覚えています。
※1……TRPGやトレーディングカードゲームの制作や翻訳を手掛けるクリエイター集団・グループSNEの代表。グループSNEについては水野良氏もその設立に参加している(その後1997年に独立)。 ※2……1977年に発売されたSF世界を舞台にしたTRPG。 ※3……『ダンジョンズ&ドラゴンズ』は1974年に発売された、RPGの原点となるTRPG。なかでも赤箱とは、1983年発売の『Dungeons & Dragons Basic Set』(国内版は『ダンジョンズ&ドラゴンズ セット:1 ベーシックルールセット』)のこと。 TRPGに初めて触れたときの印象はどうでしたか?
- 水野
映画や本といったエンターテインメントは一方通行で、自分の思い通りの展開にならないと「おいおい」とか「ご都合展開だな」とか突っ込みたくなるときがあります。でも、TRPGは自分が介入することによって物語が変化していくというインタラクティブ性があり、「こんなにおもしろいエンターテインメントがあるのか!」とびっくりしました。また、最初にプレイしたときのゲームマスター(GM)がとてもうまい方で、シナリオも非常によくできていたので、「TRPGはおもしろい!」と一発でハマりましたね。
ちなみに、読者の選択で展開が変わる“ゲームブック”についてはいかがでしたか?
- 水野
最初のころの『ファイティング・ファンタジー』や『ソーサリー』の最初の3部作(※)は遊んだのですが、そこまでハマらなかったですね。
※『ファイティング・ファンタジー』は1982年に『火吹山の魔法使い』が発売されて以降、計59冊が刊行されたゲームブックシリーズ。『ソーサリー』もその一環だが、前述の59冊とは別シリーズとして4部作が刊行されている。 自由度の高いTRPGのほうが好みだったということでしょうか?
- 水野
はい。自由度が高く、自分の介入する余地が大きいところこそが、TRPGの圧倒的なおもしろさですから。さらに“ひとつのセッションをみんなで創る”というクリエイティブな部分がとても楽しかったですし、それに関わることができるのがすごく新鮮でした。
コンピュータRPGもインタラクティブ性が魅力ですが、“GMとプレイヤーがみんなで創る”という点は、TRPGならではの要素かもしれませんね。
- 水野
ただ、TRPGは自由度が高いぶん、想像力がすごく必要だったりします。そのあたりが難しさでもあり、魅力だと言えるでしょう。ですからTRPGの自由度の高さに魅入られた人間としては、単純にストーリーを追いかけるタイプのコンピュータRPGは少し苦手だったりしますね。
コンピュータRPGも徹夜するほど熱中した
コンピュータRPGと言えば、過去のインタビューで拝見したのですが、『ウィザードリィ』(※)にすごくハマったと語られていました。
※1981年にApple II用のソフトとして発売された3DダンジョンRPG。同年に発売された『ウルティマ』と並んで、その後のコンピュータRPGに大きな影響を与えた。- 水野
まだTRPGをやり込んでないころに遊んだということもありますが、『ウィザードリィ』は圧倒的におもしろかったですね。
ということは、TRPGと『ウィザードリィ』に触れたのは同時期だったのでしょうか?
- 水野
『ウィザードリィ』も、大学生のころに安田さんの家で遊ばせてもらったんですよ。安田さんと知り合ってから、安田さんの家でたびたびボードゲーム会をするようになったのですが、その際はいつも安田さんが寝た後にパソコンをお借りして、朝まで『ウィザードリィ』で遊んでから帰るという感じでした。そのために自分用のデータも作らせてもらって(笑)。
安田さんの家で徹夜するくらい熱中していたと(笑)。
- 水野
その後、大学4年生のときにゲームサークルを作ったのですが、そのころにはApple II がコンパクトになったApple IIcというパソコンが発売されて、それを購入しました。当時で30万円くらいしたのかな? とても高価でしたがなんとか購入して、その後は『マイト・アンド・マジック』(※)などの海外のRPGをひたすら遊んでいました。
※1987年にApple II用として発売されたコンピュータRPG。マップの広さや自由度の高さで人気を博した。 当時はまさにTRPGとコンピュータRPGの両方で、いろいろなゲームを体験されていたのですね。
- 水野
そうですね。そのころは安田さんの家だけでなく、京都大学のSF研がゲームサークルと化していたので、文字通りに“おじゃま”して遊ばせてもらっていました(笑)。そこにいたメンバーには、のちにグループSNEの仲間になる人も多かったですね。その後は大学卒業を機にゲーム三昧の生活から足を洗おうとも思いましたが、洗いきれずにこの業界にいるという感じです(苦笑)。

『FFI』を超えるRPGはない
コンプティーク(※1)で『D&D』をベースにした誌上リプレイ企画として『ロードス島戦記』(※2)が始まったのは、水野先生が大学を卒業されて間もないころです。この企画が生まれたきっかけは、どのようなものだったのでしょうか?
※1……角川書店(現KADOKAWA)から1983年に刊行された雑誌。当時からパソコンやゲーム情報を主体としつつ、さまざまなコンテンツを取り上げていた。※2……1986年に『D&D』の誌上リプレイとしてスタートし、独自の世界観やキャラクターが人気となった企画。その後水野良氏によって小説となり、以降アニメ化、ゲーム化も含めて大ヒット作となった。- 水野
まずコンプティーク編集部からの依頼がグループSNEに来て、それを安田さんが受けた形だったと思います。そこで『D&D』をベースにプレイすることになったのですが、ほかの人たちは『AD&D』(※)ばかり遊んでいて、『D&D』のGMをできるのが僕しかいなかったんです。そこで僕がGMとしてセッションして、リプレイ原稿を書いて安田さんにチェックしてもらう……という形で連載が開始しました。そのときは、あれほど人気が出るとは思いませんでした。
※『アドバンスド・ダンジョンズ&ドラゴンズ』。『D&D』の上級者向けバージョン。 当時はいち読者としてリプレイを読みましたが、TRPGをプレイしたことがなくても実際に自分が体験したかのように感じられて、「ああ、こういう楽しさがあるゲームなんだ」と理解できました。
- 水野
ありがとうございます。もちろん、あの企画については実際のプレイの内容に手を加えていて、読み物としておもしろくなるような演出も入っていますし、読者からは「実際に遊んでみると、あんなにうまくはいかなかった」と苦労された話も聞きました。ただ、執筆当時はTRPGというジャンルが定着する前で、こういった企画がほとんどない時代でしたから、「まずは読み物としておもしろくなるように意識しないとダメだろう」と思ったんです。ですから、それぞれのキャラクターはプレイヤーをモデルにしつつも、名前がなくてもどのキャラクターが話しているかがわかるように、キャラクター性を加えて書きました。
そこで、のちに小説でも活躍するキャラクターたちが生まれたわけですね。
- 水野
当時の僕はまだ駆け出しですから、自分なりに志を持って書いてはいたものの、技術的な問題もあってたいへん拙い原稿で……いま読んだら黒歴史ですよ(苦笑)。でも、本当にありがたいことに多くの方から反響があり、そのおかげで第2部、第3部と続けることができました。それがすべての始まりになります。
『コンプティーク』で『ロードス島戦記』のリプレイ企画が始まった1986年は、『ドラゴンクエスト』が発売された年でもあり、その翌年には『ファイナルファンタジー』も登場しています。当時の水野先生は、そういった家庭用ゲーム機のRPGをどのように見られていましたか?
- 水野
そうか、ちょうど同時期が日本のコンピュータRPGの黎明期になるんですね。『ドラゴンクエスト』も『ファイナルファンタジー』も、ここから世界中に広がっていったと考えると感慨深いです。ただ、1作目の『ドラゴンクエスト』はプレイしませんでした。プレイヤーキャラクターがひとりだったのが、あまり好みではなかったんです。だから最初にプレイしたのは『ドラゴンクエストII』からです。
『II』は3人パーティになりましたからね。
- 水野
当時は王女を人間に戻す方法がわからなくて……。どこかでヒントを見てもとに戻すことができたのですが、あれを自力で解けなかったのは不覚でした(笑)。『II』はストーリーもすばらしく、楽しかったですね。その後のシリーズもいくつか遊んでいますが、『II』がいちばん好きです。
『FF』シリーズについてはいかがですか?
- 水野
『FF』は1作目(以下、『FFI』)から遊んでいます。最初は「“最後の幻想”とは、ものすごい大層な名前をつけているなあ」と思ったのを覚えています。
登場から40周年を迎えようとしている世界的なシリーズですけれど、1作目で“ファイナル”ですしね(笑)。
- 水野
僕はそれまでパソコンでゲームを遊んでいたこともあり、「ファミコンのスペックではたいしたものはできないだろう」という先入観があったんです。でも、『FFI』はファンタジーやSFの要素がたくさん詰まっていてすごかった。シナリオもすごく好きで、本当に究極のRPGだと思いますし、いまだにこれを超えるものはないんじゃないかと思っています。自分にとってのスタンダードなRPGとしての完成系は『FFI』かもしれません。あ、でも『FFXI』は別格ですよ、別格(笑)。

オンラインゲームについては、『FFXI』の前にプレイした作品はありましたか?
- 水野
じつはないんです。オンラインゲームは本当に『FFXI』が初めてでした。もちろん『ファンタシースターオンライン』や『ウルティマオンライン』、『ディアブロ』といった話題作の話を聞くことはありましたが、オンラインで遊ぶのはなんだか怖くて……。
当時のオンラインゲームは、最初の一歩に勇気がいるかもしれません。
- 水野
僕はどちらかというとコミュニケーションが得意なタイプではなく、知らない人と遊ぶというのはちょっとハードルが高かったんです。ただ『FFXI』については、グループSNEのメンバーから「『FFXI』がむちゃくちゃおもしろいんですよ。いっしょに遊びましょう!」と声をかけられて、「しかたないなあ……」という感じで始めました。
ヴァナ・ディールで生きられる喜び
では、いよいよ『FFXI』でどのような冒険をされたかをうかがっていきます。まず、スタートした時期はいつごろだったのでしょうか?
- 水野
『ジラートの幻影』が発売されてすぐですね。いろいろな人に助けられながら遊んでいました。そこから、『アドゥリンの魔境』が出た少し後まで遊んでいたかと思います。このインタビューのために少し復習もしたのですが、けっこう忘れていますね(苦笑)。
『アドゥリンの魔境』の発売からも、すでに10年以上経っていますからね……。さて話を戻しまして、プレイ開始時に選んだ所属国、種族、性別、ジョブについてお聞かせください。
- 水野
所属はサンドリアで、ヒュームの女性、ジョブは白魔道士でした。後衛職で遊びたかったので、能力的にバランスのいいヒュームを選びましたが、女性を選んだことはあとあと少し後悔しましたね。
それはなぜですか?
- 水野
海外のプレイヤーに口説かれるんですよ(苦笑)。
さらに白魔道士はモテましたからね(笑)。
- 水野
前情報として「白魔道士はレベル上げパーティにすぐ誘われますよ」と聞いていたので白魔道士を選んだのですが、最初のころはソロでなかなか敵が倒せなくてたいへんでした。パーティを組むようになってからは、ケアルを連打する日々でしたね。
所属国はなぜサンドリアを選んだのですか?
- 水野
う〜ん……。ちょっと思い出せないですね。“エルフと似た種族の国”だからというのは、理由としてあったかもしれません。
最初にヴァナ・ディールの地に降り立ったときの印象はいかがでしたか?
- 水野
鳥肌が立ちましたよ。初めてTRPGに出会ったときと同じくらいのインパクトでした。僕らのようにクリエイティブ側にいる人間や、創作が好きなタイプの人は、「好きな世界の中に入りたい」という願望が少なからずあると思いますが、まさに“それが叶う世界”だと感じました。「俺もこの世界で生きられるの? ここで生きていいの? 理想の世界だ!」、「なぜここまでMMORPGを敬遠してきたんだろう……」と思いましたよ。
(笑)。
- 水野
もちろんオンラインゲームは初めてでしたので、最初は常識もリテラシーもなく、いろいろとやらかしたこともあったかもしれません。フィールドでミスラのプレイヤーに声をかけられて、思わず挙動不審になったりとか、「ロンフォールの音楽はステキだなあ」と思って歩いていたらオークに追いかけられたりとか。
「あるある話」ですね(笑)。
- 水野
続くラテーヌ高原で雄羊に踏みつぶされたり、エリアごとにエピソードを語れそうです。どこもかしこも思い出に溢れているというのは、すばらしいことですよ。
そういえば、最初に選んだのは白魔道士とのことでしたが、のちのメインジョブは赤魔道士とお聞きしました。
- 水野
どういったものをメインジョブと呼ぶのかにもよりますが、さまざまな場面で赤魔道士を求められることが多かったことと、とくに装備にこだわりがあったジョブという点で、メインジョブは赤魔道士ということにしています。ほかにも後衛ジョブはひと通り使えるようにしていて、白魔道士、黒魔道士、学者もレベル99にしました。
前衛職はいかがでしたか?
- 水野
戦士、シーフ、ナイト……ほかにもいくつかのジョブをレベル99にしていたと思います。実際のコンテンツ攻略において前衛で呼ばれることはなかったですが。あと、ひとりで遊べる獣使いも好きでしたね。
たくさんのジョブで遊ばれていたのですね。
- 水野
全部は育てきれませんでしたが、多くのジョブで遊んでいました。青魔道士も『FF』シリーズで好きなジョブでしたから、『FFXI』でも育てていました。青魔道士はラーニングが楽しいので、どの作品でもやり込んじゃうんですよ。『FFXI』の青魔道士はラーニングツアーでなかなか魔法が覚えられなくて、けっこう泣きましたけれど(苦笑)。