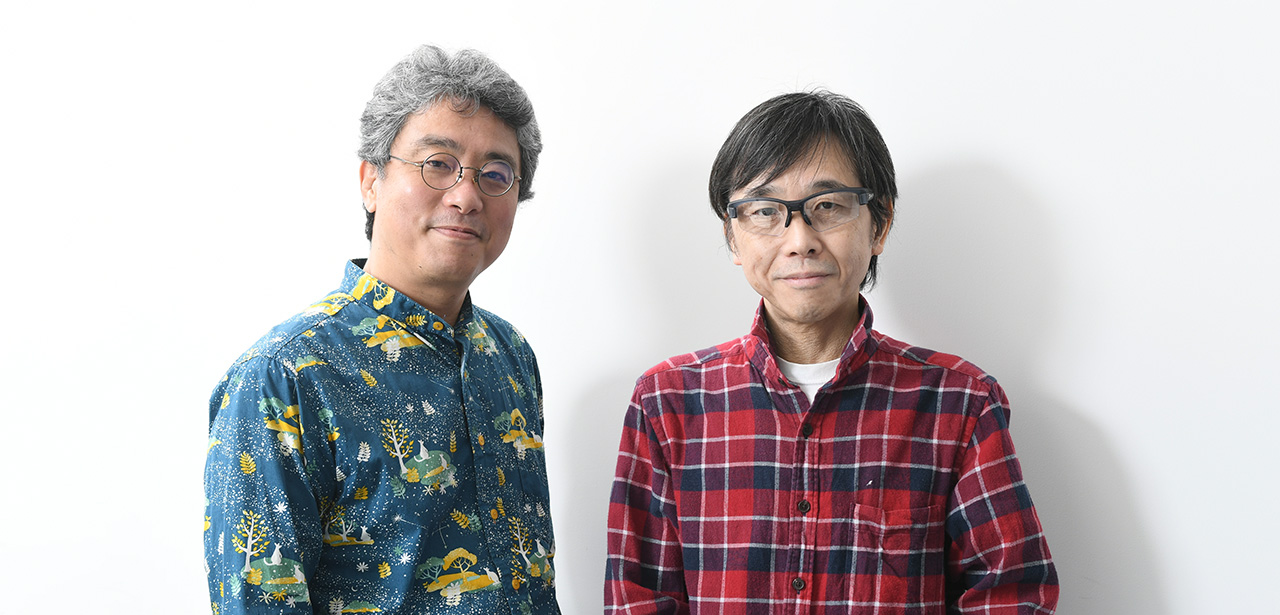松井プロデューサーが、『ファイナルファンタジーXI』(以下、『FFXI』)とゆかりのある人物と対談を行う“プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’DIEL-”。第8回の対談相手は、『FFXI』において『ジラートの幻影』までのストーリーを手掛けた加藤正人さん。『FFXI』の大きな魅力である、“MMO(多人数同時参加型オンライン)RPGに本格的なストーリーを盛り込む”という要素は、どのようにして構築されていったのか? その流れの中で、重要なカギを握るのが加藤さんだ。対談のパート1となる本稿では、加藤さんにとっての“ゲーム内にストーリーを導入すること”の原点や、スクウェア(現:スクウェア・エニックス)に入社するまでの経緯を語っていただいた。
数多くのゲームで企画・世界設定・シナリオ・演出などを手掛けるクリエイター。スクウェア在籍時は『クロノ・トリガー』、『ゼノギアス』、『クロノ・クロス』などを手掛けたのち、『FFXI』でストーリー全般を担当。『FFXI』初の拡張データディスクとなる、『ジラートの幻影』までのプロットをまとめ上げた。またスクウェア退社後も、2009年に追加シナリオ3部作『石の見る夢』、『戦慄!モグ祭りの夜』、『シャントット帝国の陰謀』のシナリオを担当。現在はグリーに所属し、シナリオ・演出を手掛けたシングルプレイ専用RPG『アナザーエデン 時空を超える猫』が好評を博している。
ゲームに“物語”を盛り込めることに興味を引かれゲーム業界へ
- 松井
おひさしぶりですね。プロデューサーセッションではこれまでさまざまな方と対談をしてきたのですが、開発初期のころの話になると加藤さんの名前が必ずと言っていいくらい出ていたんですよ。今日はようやく“ご本人登場!”といった感じです。改めてよろしくお願いいたします。
- 加藤
そうなんですか(笑)。こちらこそ、よろしくお願いいたします。
まずは、加藤さんがゲーム業界に入られるまでの話を振り返っていただけますか。そもそも、物語というものに興味を持たれたのはいつごろだったのでしょう?
- 加藤
僕は、子どものころから絵を描いたり本を読んだりするのが大好きでした。それで、将来は絵か文学のどちらかで “モノ作り”に携わりたいと考えていました。そんな中、大学は美術大学を目指していたのですが、試験で不合格になってしまったので、気持ちを切り替えて文学部のある大学に進学したんです。
- 松井
美術と文学、両方が選択肢にあったのがすごいですね。
- 加藤
その後、大学を無事に卒業したものの、なんとなく定職に就く気にはなれず、アニメーターの下請けのアルバイトを始めました。このアルバイトは出来高制で、原画を1枚描いて何十円という世界です。どんなにがんばっても、月に6〜7万円にしかならないんですよ。ですから、当時同居していた妹に、アパートの家賃を肩代わりしてもらう有様で……(苦笑)。こんな生活を長く続けるわけにはいかないなと思っていました。
それは兄として肩身が狭いですね(苦笑)。
- 加藤
そんなときに、何気なく『ドラゴンクエストII』(以下、『DQII』。※)をプレイして、大きな衝撃を受けました。ゲームの中では自分が物語の主人公になれて、自分が好きなように行動でき、それによって物語の展開も変わっていく。映画や小説とは違って自分が主体となり、現実世界とは別の人生を体験できるわけです。いまでこそRPGは当然のように知れ渡っていますが、当時の僕は『DQII』が初めてのRPGだったので、本当に衝撃的でした。
※1987年にファミリーコンピュータ向けに発売されたRPG。前年発売の『ドラゴンクエスト』の続編にあたり、本作で初めてパーティバトルを採用した。 - 松井
加藤さんのRPGの原体験は、『DQII』だったのですね。
- 加藤
そうですね。この出会いによって、“お話を書くことでもゲームの開発に携われる”という気づきがありました。そんな折にテクモ(当時)が人材募集広告を出していたのを見かけて、思わず応募したんです。
アクションゲームにストーリーを盛り込むというチャレンジ
- 松井
テクモではどういったお仕事をされていたのですか?
- 加藤
最初に関わったのは、マンガ原作のサッカーゲームでした。このゲームでは、試合中のドリブルやシュートなどの各シーンを短いアニメーションで表現しているのですが、この絵を描ける人が当時のテクモにはいなかったんです。僕はアニメーターのアルバイトをしていたこともあり、この作業にまさに適任でした。
- 松井
最初はデザイナーとしての仕事だったのですね。あのゲームのアニメーションは、短いながらも印象に残っています。
- 加藤
マンガが原作というのもあり、ドリブルのオーバーな動きなどは、いま思い出すとおもしろいですよね(笑)。そして、このサッカーゲームの開発を無事に終えたところで、ちょうどそのころアメリカで忍者が流行っていたことを受けて、今度は“忍者のアクションゲーム”の開発プロジェクトが立ち上がったんです。当時テクモに在籍していた吉沢秀雄さん(※)という方がディレクターで、僕はグラフィック担当として参加しました。
※吉沢秀雄氏はおもにテクモやナムコ(当時)で数多くのゲームのディレクション、プロデュースを手掛けたクリエイター。
- 松井
そのゲームも覚えています。日本古来の“忍者”というより、海外の方から見た“ニンジャ”のイメージが存分にフィーチャーされていましたよね。
- 加藤
あれは、吉沢さんが「単に忍者が出てくるだけのふつうのアクションゲームはイヤだ!」と、とくにこだわった部分なんですよ。だから、現代を舞台にしたゲームなのに、主人公の青年に「おのれ邪鬼王!」などと言わせてしまう(笑)。そして実際に発売したら、あのステレオタイプの忍者が大ウケで。仮にふつうの忍者が主人公のゲームだったら、ここまで語り継がれるような作品にはなり得なかったでしょうね。
あのシリーズは、現在も3Dアクションゲームとしてその精神的な部分が引き継がれていますが、人気が続いているのは第1作のインパクトが大きかったからだと思います。
- 加藤
その忍者アクションゲームの開発中、自分にとって大きな影響を与える事件がありました。それは、吉沢さんがアクションゲームに“ストーリー”を盛り込んだことです。吉沢さん自身、もともと映画業界を志していたこともあり、ゲームならではのストーリーテリングの手法を模索していました。そこで、その忍者アクションゲームでは、ひとつのステージをクリアしたときに、カットインでストーリーを見せる流れにしたのです。
元アニメーターの加藤さんにとっては、興味が湧くアイデアだったと。
- 加藤
それはもう、がぜん興味が湧きましたよ。ですので、もともとはグラフィック部分のみを担当する予定だったのですが、最終的にはカットインのコンテ切りなども含め、かなり幅広く担当しています。これを経験したことで、“ストーリー性のあるドラマをゲームに盛り込むことには価値がある”ということを確信しました。
- 松井
しかも加藤さんにとっては、幼少期から興味のあった“絵”と“ストーリー”の両方に関わることができたわけですよね。
- 加藤
はい。そこで続編では、ストーリーの原案も書かせてもらえるようになりました。同時にグラフィックも担当していたので多忙を極めましたが、とても充実した日々でしたね。ゲームの可能性がどんどん広がっていくのを実感していました。
- 松井
その後は、テクモからガイナックスへ移られたのでしたっけ?
- 加藤
テクモで3年くらい働いていましたが、次第に業務に対して行き詰まりを感じるようになりました。そんな中、プライベートでとある育成シミュレーションゲームを遊んで、これはすごいなと衝撃を受けました。そこで、開発元のガイナックスに飛び込みで面接を受けて、入社を希望しました。
当時はこのゲームをきっかけに、育成シミュレーションゲームのブームが起こりましたよね。
- 加藤
そして入社後、意中の作品の続編に関わることができました。僕が前作をプレイしたとき、エンディングのバリエーションに物足りなさを感じていたので、続編ではこの部分を強化したいと考えました。そこで、キャラクターのパラメータに応じてフラグを立てるようにし、そこからさまざまな展開を用意するなど、各方面を大幅に強化しました。そのほかの各種イベントやマップデザインなども僕が担当しています。
その育成シミュレーションゲームは家庭用ゲーム機向けにも移植されましたし、長期にわたって人気を博していました。
- 加藤
でも残念なことに、当時のガイナックスのゲーム部門は規模が小さくて、開発ラインが1、2本しかなかったんです。しかも、すでに著名なクリエイターさんが在籍しているので、僕のような新参者ががんばっても、頭角を表すことは難しい。ですので、もっと大きなゲームメーカーで働きたいと思い、今度はスクウェア(※現:スクウェア・エニックス)に狙いを定めたのです。